
<HITACHI SR11000>

| 仕様策定委員長 |
| 大学院自然科学研究科長 |
| 教授 島倉 信 |

| 総合メディア基盤センター |
| 副センター長 教授 井宮 淳 |
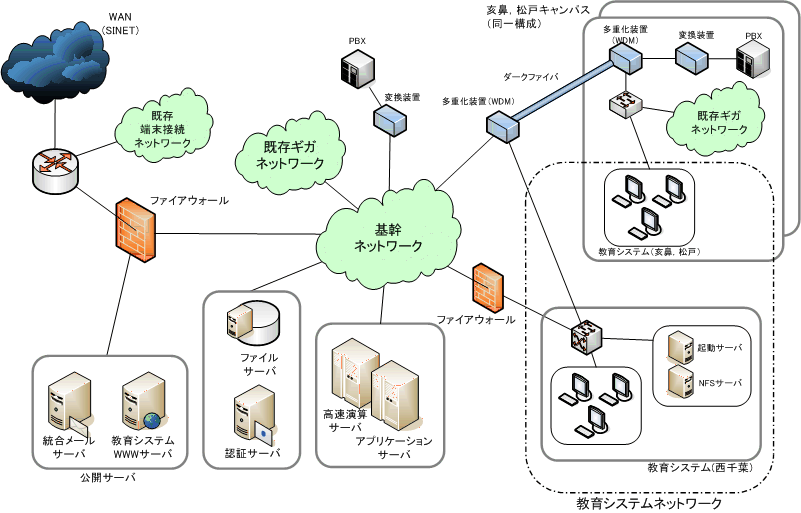
 |  |
| <教育システム利用説明会の様子> | |
(研究課題名)多田 充 助教授
スーパーコンピュータとPCの連携による鉄筋コンクリート造建物の3次元非線形FEM解析法の開発
(研究の目的)
3月から導入予定のスーパーコンピュータとPCを連携させ,大規模な建築構造の非線形FEM解析をスーパーコンピュータで解き,その基になる部材の解析や,入出力のプレ・ポストプロセッサーをPCで利用する方法を開発する。この研究は,一般ユーザーにスーパーコンピュータの新しい利用を促す位置づけも意図したものである。
(研究課題名)井宮 淳 教授
数論的問題に関する計算困難性の仮定を必要としない電子認証に関する研究
(研究の目的)
現在一般的に利用されている公開鍵暗号系は,素因数分解問題や離散対数問題などの数論的問題の計算量的困難性を仮定した上で安全性が示されるものがほとんどであるが,これらの問題は,量子計算機を用いると多項式時間で計算できることが示されているので,将来的に量子計算が実現すると安全に利用することができません。
本研究では,数論的問題を仮定せずに,単にP≠NPであれば安全性が示される,NP完全問題に基づく公開鍵暗号系に関する研究を行う。
(研究課題名)今泉貴史 助教授
無線LAN監視システム開発のための自在LANシステムの開発+研究会開催
(研究の目的)
本研究では,無線によって個体間の通信が可能な移動ロボットを複数台用意して,現実のAdHoc型ネットワークの運用と同様に,端末が自由に移動することができる実験用の閉 じたネットワークを構築する。この実験システムを利用して,現在,固定型ネットワークに対して開発しているネットワーク監視,運用システムを,無線LAN型AdHocネットワークの上でも適用するための間題点を,実験を通じて探る。
(研究課題名)酒井智弥 助手
同報通信を制限した機器を用いる情報コンセント構築法
(研究の目的)
情報コンセント構築の際には,接続端末を守るための方策,接続端末からの攻撃を防ぐ方策などさまざまな処理が必要となる。外部と内部との通信であれば,ファイアウォールを設けることで対処できるが,情報コンセントにつないだ端末同士の通信に関しては制限できないため,公衆ネットワーク内でウイルスが蔓延してしまう危険がある。同報通信を制限した機器を用いることで,ウイルスの蔓延を防止することを目的とする。
(研究課題名)宗宮好和 教授
総合大学におけるe-learningの導入活用に関する研究
(研究の目的)
e-learningの普及において問題となる,システムの互換性,教材の移植性,コスト,学習効果,著作権等に関する調査を行う。また,e-learningの基盤提供とコンテンツ開発による利用促進に取り組む。
(研究課題名)神谷友久 助教授
Multiple e-Lerning contentsの制作・開発に関する研究
(研究の目的)
ある講義の1学期間の構成は(最大)1回90分x15回である。まずその内容(コンテンツ)をデジタル化する。コンテンツには,各種のリンクが張られる。教師の注釈,参考文献,文献の解説,ときにはインターネット上のサイトなど。いま構想するe-Learning contentsは,そこに他の講義をリンクさせるものである。その講義も同様にmultipleなものでなくてはならない。すなわち,一つの学問の入り口から,迷路のような,しかし,理論的関連をもつ他のサイト(=学問分野)に入っていく構造になっている。教師の共同研究が不可欠であるが,将来的なバーチャル・ユニバーシティあるいはe-Learningシステムを視野において,このようなmultiple contents制作の可能性について考えてみたい。
(研究課題名)全へい東 教授
教育効果の高いeラーニングの研究開発
(研究の目的)
近年の情報通信技術の発展を背景に,eラーニングが注目されつつある。しかしながら,その運用に必要な労力,能力,時間,コストは相当に大きく,実際の普及や活用はそれほど進んでいない。本研究開発では,従来の無機的・形式的なeラーニングから脱却し,教育効果の高い教育を行う観点から,eラーニングを実証的に研究開発する。情報処理を内容とするeラーニング教材を研究開発し,実際に授業で用い,フィードバックを行う。教育効果を高めるため,実習型とし,インタラクティブでクリエイティブなeラーニング教材を開発する。
(研究課題名)植田 毅 助教授
センサエリアネット(SeAN)の基礎検討
(研究の目的)
人や車などの動的な監視対象を確実に追跡・分析するには,複数の視点から観測することが必須である。複数の視点から観測する場合,個々のカメラの位置や姿勢を知る必要があるが,これまではもっぱら人手による作業に頼っていた。そこでこの研究では,複数のセンサをアドホックネットワークにより相互接続し,さらに自律的に互いの位置関係を求め,対象の追跡を動画像処理によって実現する「センサエリアネットワーク(SeAN)」を実現するための基礎的な検討を行う。
(研究課題名)
グリッド計算による次期情報環境基盤システムの有効利用法の探索
(研究の目的)
総合メディア基盤センターの次期情報環境基盤システムでは,Linux, Windowsがdual boot可能なPC端末が500台以上導入される。特に,普遍教育用の端末群は夏休み,後期には利用率が極めて下がることから,これらの端末を有効利用するべく,グリッド計算用のアプリケーションソフトウェアの導入も盛り込まれている。本プロジェクトでは模擬的なシステムを用いてグリッド計算を行うことにより,そのパフォーマンスの確認,ノウハウを蓄積,公開することによって,次期情報環境基盤システム上でのグリッド計算を奨励,振興することを目的とする。
| ■場所 | : | 千葉大学西千葉キャンパスけやき会館3階レセプションホール |
| ■日時 | : | 平成17年2月3日(木) 10:00 - 17:00 |
| ■プログラム | : |
| 10:00 - 10:10 | Opening(井宮淳) |
| 10:10 - 10:55 | 【招待講演】 |
| 「ユビキタスネットワーク社会創造への道筋と課題」 森川博之(東京大学) | |
| 10:55 - 11:30 | 「デジタル署名の効率化と安全性」 多田充(千葉大学) |
| (休憩) | |
| 13:00 - 13:45 | 【招待講演】 |
| 「ソフトウェアと検証技法」 青木利晃(北陸先端大学) | |
| 13:45 - 14:20 | 「P2Pネットワークにおけるコンテンツ検索メッセージのフラッディング」効率化 塩田茂雄(千葉大学) |
| (休憩) | |
| 14:50 - 15:25 | 「計算機システムの高信頼化」 北神正人(千葉大学) |
| 15:25 - 16:00 | 「ランダム点集合の分割」 井宮淳(千葉大学) |
| 16:00 - 17:00 | 全体討論 |
| 「大学院における情報科目の教育研究のあり方について」 | |
| 17:00 - | Closing |
| 日時 | : | 平成17年3月15日(火) |
| 時間 | : | 10:00〜17:00 (予定) |
| 場所 | : | 総合メディア基盤センター4階 会議室 |
| 申請期間 | : | 平成17年3月11日(金)まで |
| 申請方法 | : | 所定の申請用紙に記入・捺印の上,期日までに財務部情報課情報基盤係(センター1階受付窓口)に,直接又は学内便で提出してください。 |
| 申請書類 | : | ・ 支払責任者登録・計算機利用申請書 |
| 支払責任者となる方が提出して下さい。この申請書は,支払責任者としての登録と責任者本人の計算機利用登録との両方を兼ねています。 | ||
| ・ 計算機利用申請書 | ||
| 研究グループ利用者となる方が提出してください。支払責任者の書名捺印が必要です。 |